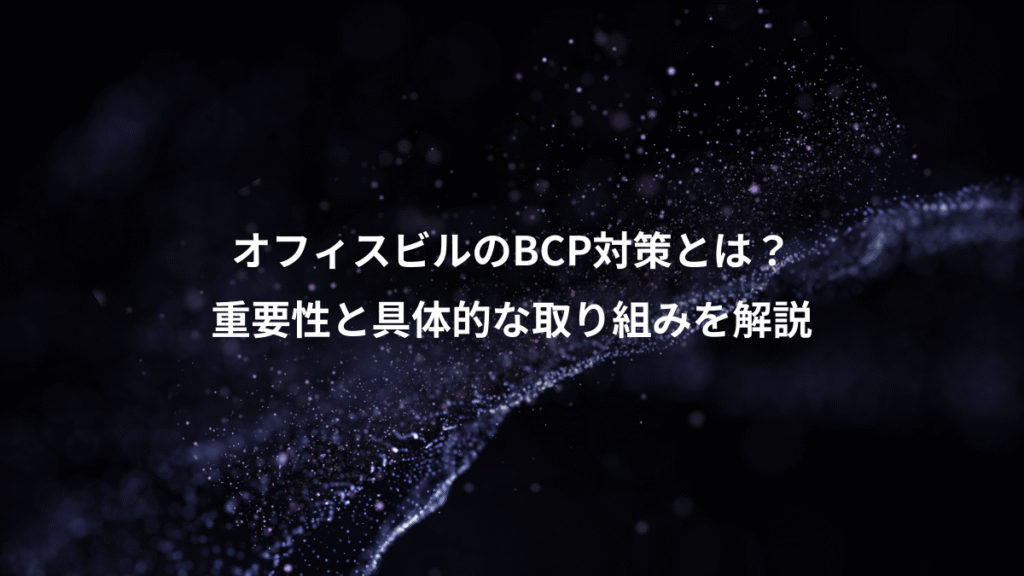現代のビジネス環境において、企業は地震、台風、豪雨、パンデミックといった予測困難な様々なリスクに常に晒されています。これらの緊急事態が発生した際、事業活動が停止してしまうと、売上機会の損失だけでなく、顧客や取引先からの信頼を失い、企業の存続そのものが危ぶまれる事態に発展しかねません。
そこで重要となるのが「BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)」です。特に、多くの従業員が集まり、事業の中核を担うオフィスビルにおいては、BCP対策の巧拙が企業の命運を分けると言っても過言ではありません。
本記事では、オフィスビルのBCP対策について、その基本的な考え方から、重要視される理由、そしてハード面・ソフト面における具体的な取り組みまでを網羅的に解説します。さらに、BCP対策に優れたオフィスビルを選ぶ際のチェックポイントや、対策を強化するための便利なツール・サービスもご紹介します。この記事を通じて、自社の事業継続性を高めるための具体的なヒントを得ていただければ幸いです。
目次
BCP(事業継続計画)とは
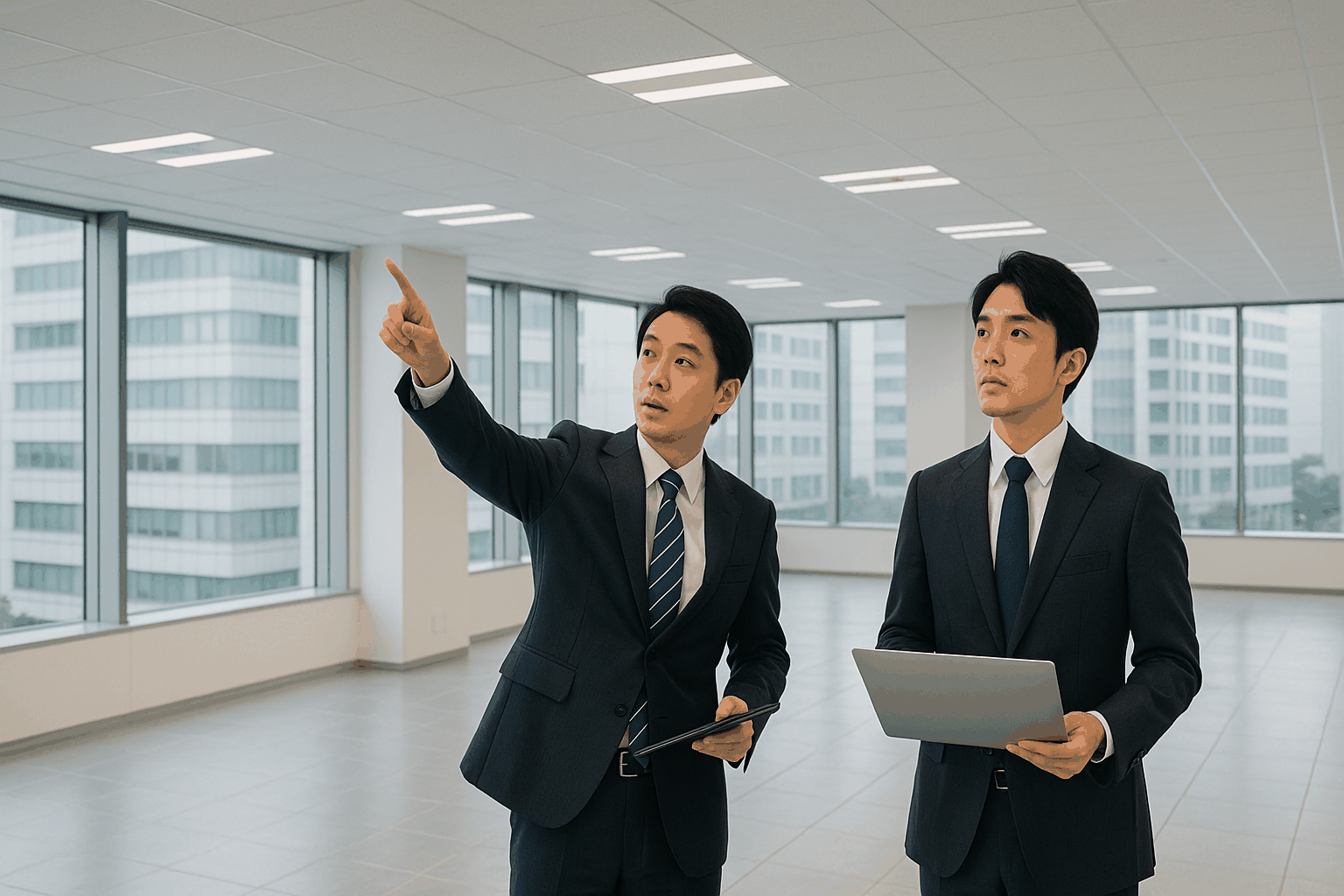
BCP対策を考える上で、まずその定義と目的を正しく理解することが不可欠です。BCPとは、英語の「Business Continuity Plan」の頭文字を取った略語で、日本語では「事業継続計画」と訳されます。これは、自然災害、大事故、感染症のパンデミック、サプライチェーンの途絶、テロ、サイバー攻撃といった予期せぬ緊急事態が発生した際に、企業が受ける損害を最小限に食い止め、中核となる事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための、方針、体制、手順などをまとめた計画書を指します。
多くの人がBCPと混同しがちなのが「防災対策」です。両者は密接に関連していますが、その目的と焦点には明確な違いがあります。
- 防災対策: 主な目的は、人命の安全確保と物的被害の軽減です。例えば、地震 발생時の避難訓練、消火設備の設置、建物の耐震補強などがこれにあたります。災害の発生そのものに備え、被害を「防ぐ」または「減らす」ことに主眼が置かれています。
- BCP(事業継続計画): 防災対策で被害を軽減した上で、さらに「事業をいかに継続・復旧させるか」という点に焦点を当てます。防災対策が「守り」の側面が強いのに対し、BCPは事業を守り、継続させるという「攻め」の視点も含まれる、より経営戦略に近い概念です。
つまり、BCPは防災対策を包含した、より広範で戦略的な取り組みと位置づけることができます。人命の安全確保が最優先であることは言うまでもありませんが、その上で、どの事業を優先的に復旧させ、そのためにはどのような資源(人材、拠点、設備、資金、情報など)が必要かをあらかじめ定めておくのがBCPの役割です。
BCPの策定は、一般的に以下のようなステップで進められます。
- 基本方針の策定: なぜBCPを策定するのか、その目的と適用範囲を明確にします。
- リスクの洗い出しと分析: 自社に影響を与えうる災害や事故などのリスクを具体的に洗い出し、その発生可能性や影響度を評価します。
- 事業インパクト分析(BIA): 各事業が停止した場合に、ビジネス全体にどのような影響(売上、顧客、ブランドイメージなど)が、どのくらいの時間経過で現れるかを分析します。これにより、優先的に復旧すべき中核事業を特定します。
- 事業継続戦略の検討: 中核事業を継続・復旧させるための具体的な方法を検討します。代替オフィスの確保、リモートワーク体制の構築、データのバックアップ、代替サプライヤーの確保などがこれにあたります。
- BCPの文書化: 検討した戦略を具体的な計画書としてまとめます。誰が、いつ、何を、どのように行うのかを明確に記述します。
- 教育・訓練の実施と定着: 策定したBCPを全従業員に周知し、定期的な訓練を通じてその実効性を検証します。
- 評価と見直し: 訓練の結果や、事業環境の変化、新たなリスクの出現などを踏まえ、BCPを継続的に見直し、改善していきます。
オフィスビルは、まさにこのBCPを実践する上での物理的な「舞台」となります。ビルの耐震性能が低ければ従業員の安全は確保できず、非常用電源がなければ事業継続に必要なITシステムは停止します。また、ビル管理会社との連携体制がなければ、災害時の情報収集や帰宅困難者対応もままなりません。このように、オフィスビルの選定や環境整備そのものが、BCPの根幹をなす重要な要素なのです。
もはやBCPは、一部の大企業だけが取り組む特別なものではありません。むしろ、経営資源に限りがある中小企業こそ、一度の被災が致命傷になりかねないため、BCPの重要性はより高いと言えるでしょう。BCP対策は単なるコストではなく、企業のレジリエンス(回復力・強靭性)を高め、不確実な時代を生き抜くための不可欠な「経営投資」であると認識することが、すべての企業の持続的成長の第一歩となります。
オフィスビルでBCP対策が重要視される3つの理由
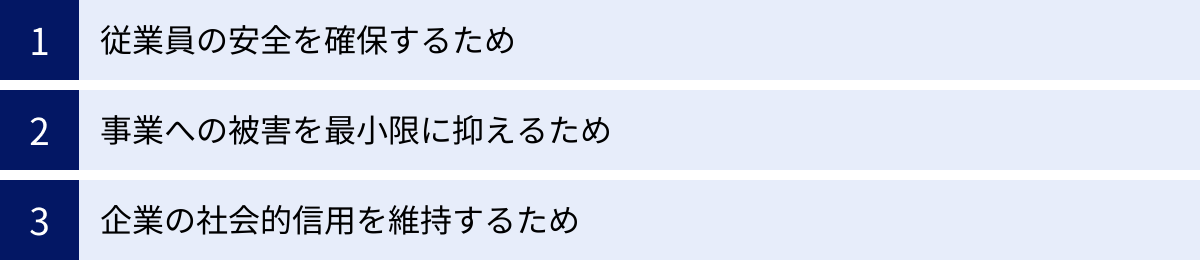
なぜ今、多くの企業がオフィスビルのBCP対策に注目し、投資を行っているのでしょうか。その背景には、単に災害に備えるという以上の、企業経営の根幹に関わる3つの重要な理由が存在します。これらを理解することは、BCP対策をコストではなく、未来への投資として捉え直すきっかけとなるでしょう。
① 従業員の安全を確保するため
BCP対策において、最も優先されるべきは「従業員の安全確保」です。事業継続を語る以前に、企業の存立基盤である人材を守ることは、経営の絶対的な前提条件であり、法律上も企業には従業員に対する「安全配慮義務」が課せられています。この義務を怠ったと判断されれば、企業は法的な責任を問われる可能性もあります。
オフィスビルという閉鎖された空間では、災害時に様々な危険が従業員を襲います。
- 地震: 強い揺れによるオフィス什器(キャビネット、コピー機など)の転倒や移動、天井材や照明器具の落下、窓ガラスの飛散などが考えられます。これらは従業員の負傷に直結する深刻なリスクです。
- 火災: 地震の二次災害として、あるいは漏電や放火など、様々な原因で火災が発生する可能性があります。初期消火の遅れや不適切な避難誘導は、多数の犠牲者を出す大惨事につながりかねません。
- インフラの停止: 停電によってエレベーターが停止し、高層階の従業員が閉じ込められるリスクがあります。また、断水によってトイレが使用不能になれば、衛生環境が急激に悪化し、感染症のリスクも高まります。
こうした直接的な危険から従業員を守るために、BCPの一環としてオフィスビルでの安全対策を講じることは不可欠です。具体的には、建物の耐震性能の確認、什器の固定、避難経路の確保と周知、定期的な避難訓練の実施、救護用品の備蓄などが挙げられます。
さらに、従業員の安全確保は、物理的な側面だけにとどまりません。災害発生直後、従業員が最も不安に感じるのは「自分や家族の安否」と「会社の状況」です。安否確認システムを導入し、迅速に従業員とその家族の無事を確認できる体制を整えることは、従業員の精神的な不安を和らげ、安心感を与える上で非常に重要です。
従業員の安全を最優先する姿勢を明確に示すことは、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)やロイヤルティ(会社への忠誠心)を高める効果も期待できます。「この会社は自分たちのことを本当に大切にしてくれている」と感じることができれば、従業員は安心して業務に集中でき、いざという時には一丸となって会社の危機を乗り越えようと努力するでしょう。逆に、安全対策が不十分なオフィスで従業員を働かせている企業は、人材の流出を招き、長期的な競争力を失うことにもなりかねません。
このように、従業員の安全確保は、法的・倫理的な義務であると同時に、企業の最も重要な資産である「人」を守り、組織の結束力を高めるための根幹的な取り組みなのです。
② 事業への被害を最小限に抑えるため
緊急事態が発生した際に事業が停止すれば、企業は深刻な経済的ダメージを受けます。この被害を最小限に抑え、事業の早期復旧を可能にすることが、BCPの核となる目的です.
事業停止がもたらす被害は、直接的なものと間接的なものに大別されます。
- 直接的な被害:
- 売上の逸失: 製品の生産やサービスの提供が停止することによる、直接的な売上・利益の減少。
- 設備の損壊: オフィス設備、IT機器、製造機械などが物理的に破損することによる復旧コスト。
- データの消失: サーバーのダウンや破損による、顧客情報や業務データといった重要な無形資産の喪失。
- 間接的な被害:
- 顧客離れ: 製品やサービスを供給できない期間が長引くことで、顧客が競合他社に流れてしまうリスク。
- サプライチェーンの混乱: 自社が部品を供給できなくなることで、取引先の生産活動にまで影響を及ぼす。逆に、仕入先が被災し、自社の生産が止まるケースも考えられます。
- 機会損失: 競合他社が事業を継続している中で、自社だけが停止していると、市場シェアを奪われる可能性があります。
これらの被害を最小化するために、BCPでは「事業インパクト分析(BIA)」という手法を用いて、どの事業が停止すると会社に最も大きな打撃を与えるか(=中核事業)を特定します。そして、その中核事業ごとに「目標復旧時間(RTO: Recovery Time Objective)」と「目標復旧レベル(RPO: Recovery Point Objective)」を設定します。
- 目標復旧時間(RTO): 「この事業は、災害発生後、何時間(何日)以内に復旧させなければならないか」という時間的な目標です。例えば、オンラインストアの受発注システムなら「3時間以内」、基幹業務システムなら「24時間以内」といった具体的な目標を設定します。
- 目標復旧レベル(RPO): 「どの時点のデータまでなら失われても許容できるか」というデータ損失の許容範囲を示す目標です。例えば、バックアップの頻度に関わり、「最悪でも1時間前のデータまでは復旧させたい」といった目標を設定します。
これらの目標を達成できるかどうかは、オフィスビルの設備に大きく依存します。例えば、RTOを「3時間」と設定しても、オフィスが停電し、非常用電源がなければサーバーは起動できず、目標達成は不可能です。データセンターを遠隔地に分散させたり、クラウドサービスを活用したりすることも有効な手段ですが、本社機能が麻痺してしまっては、復旧の指揮を執ることすらできません。
BCP対策が施されたオフィスビルは、事業継続のための強固な基盤となります。 72時間連続稼働する非常用電源があれば、外部の電力供給が途絶えても3日間はサーバーやPCを動かし続けることができます。耐震性の高い建物であれば、重要なIT機器が物理的に破損するリスクを低減できます。複数の通信回線が引き込まれていれば、一つのキャリアがダウンしても、別の回線で通信を確保できます。
このように、事業への被害を最小限に抑えるという観点から、オフィスビルのハードウェア(建物や設備)とソフトウェア(復旧計画や体制)の両面から対策を講じることが、企業の存続と成長にとって極めて重要なのです。
③ 企業の社会的信用を維持するため
現代の企業経営において、「社会的信用」は売上や利益と同様に、あるいはそれ以上に重要な経営資源です。BCP対策は、この目に見えない、しかし決定的に重要な資産を守り、維持するためにも不可欠な取り組みです。
企業は、顧客、取引先、株主、金融機関、地域社会といった様々なステークホルダー(利害関係者)との信頼関係の上に成り立っています。緊急事態が発生した際の企業の対応は、これらのステークホルダーからの評価に直結します。
まず、顧客や取引先からの信用という観点では、製品やサービスを安定的に供給し続ける責任があります。特に、現代のビジネスは複雑なサプライチェーン(供給網)によって成り立っており、一社の事業停止が川上から川下まで、広範囲にわたって影響を及ぼす可能性があります。自社が重要な部品の供給を担っている場合、その停止は取引先の生産ライン全体をストップさせてしまうかもしれません。
近年、多くの企業は取引先を選定する際に、その企業のBCP対策の状況を評価項目の一つとして重視するようになっています。「災害に強い企業と取引したい」と考えるのは当然であり、BCP対策を整備していることは、それ自体が企業の競争力となり、信頼性の証となります。 逆に、BCPが未整備であると、重要な取引を失うリスクや、新規契約の機会を逃すことにもつながりかねません。
次に、株主や投資家からの信用も重要です。彼らは、企業が長期的に安定して成長し、利益を生み出すことを期待しています。BCPは、予期せぬ事態に対する企業の「レジリエンス(強靭性)」を示す指標であり、投資判断における重要な非財務情報の一つと見なされ始めています。災害によって甚大な被害を受け、事業再開の目処が立たないような企業は、企業価値が大きく損なわれ、株価の下落や資金調達の困難を招くでしょう。
さらに、地域社会からの信用も忘れてはなりません。災害時、企業は地域社会の一員としての役割を果たすことが期待されます。例えば、オフィスビルが帰宅困難者のための一時滞在場所を提供したり、備蓄している食料や水を地域住民に提供したりといった貢献活動は、企業の社会的評価を大いに高めます。こうしたCSR(企業の社会的責任)活動は、平時における良好な地域関係の構築にも繋がり、結果として事業活動を円滑に進める上での土台となります。
緊急事態は、いわば企業の「真価」が問われる瞬間です。平時には見えにくい、危機管理能力や従業員への配慮、社会への責任感といったものが、災害対応を通じて白日の下に晒されます。日頃からBCP対策をしっかりと講じ、いざという時に迅速かつ的確に行動できる企業は、ステークホルダーからの信頼を一層深め、危機を乗り越えた後には、以前にも増して強固な事業基盤を築くことができるでしょう。このように、社会的信用を維持・向上させるという点においても、オフィスビルのBCP対策は極めて重要な経営課題なのです。
オフィスビルのBCP対策|ハード面の具体例
オフィスビルのBCP対策において「ハード面」とは、建物そのものの構造や、事業継続を物理的に支える設備を指します。これらは、一度オフィスを構えると容易には変更できないため、移転や新設の際には特に慎重な検討が必要です。ここでは、代表的なハード面の対策について、その内容と重要性を具体的に解説します。
建物の構造(耐震・制震・免震)
日本は世界有数の地震国であり、建物の地震対策はBCPの根幹をなす最も重要な要素です。建物の揺れを制御する技術は、主に「耐震」「制震」「免震」の3種類に分類され、それぞれに特徴があります。
| 構造の種類 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 耐震構造 | 柱や梁、壁などの構造部材を強固に作り、建物の強度で地震の力に耐える構造。 | ・最も一般的でコストが比較的安い。 ・多くのビルで採用されている。 |
・建物の揺れ自体は大きくなるため、上層階ほど揺れが増幅されやすい。 ・内部の什器転倒や設備の損傷リスクが高い。 ・繰り返しの揺れで建物にダメージが蓄積しやすい。 |
| 制震構造 | 建物内にダンパーなどの「制震装置」を設置し、地震のエネルギーを吸収して揺れを小さくする構造。 | ・耐震構造に比べて建物の揺れを20~30%程度低減できる。 ・上層階の揺れを効果的に抑えられる。 ・風揺れにも効果がある。 ・耐震補強として既存のビルにも導入しやすい。 |
・免震構造に比べると揺れ低減効果は限定的。 ・ダンパーの設置スペースが必要。 |
| 免震構造 | 建物の基礎部分に積層ゴムやダンパーなどの「免震装置」を設置し、地震の揺れを建物に直接伝えないようにする構造。 | ・建物の揺れを1/3~1/5程度にまで大幅に低減できる。 ・建物自体の損傷が少なく、内部の什器転倒や設備破損のリスクが極めて低い。 ・事業継続性が最も高い。 |
・コストが最も高い。 ・地盤が強固であることなど、設置に条件がある。 ・定期的なメンテナンスが不可欠。 |
どの構造を選ぶべきかは、企業の事業内容によって異なります。 例えば、精密機器を扱う研究開発施設や、24時間365日稼働し続けるデータセンターなど、わずかな揺れでも事業に致命的な影響が出る場合は、コストが高くても免震構造が最適です。一方、一般的なオフィス業務が中心であれば、制震構造でも十分に事業継続性を高めることができます。耐震構造のビルを選ぶ場合でも、1981年6月1日に導入された「新耐震基準」を満たしていることは最低条件であり、さらに建物の耐震性能を詳細に評価した「耐震診断」の結果を確認することが重要です。
また、構造部材だけでなく、天井や照明、間仕切り壁といった「非構造部材」の耐震対策も見逃せません。これらが落下・転倒すると、直接的な人的被害や避難経路の閉塞につながるため、ビル選定時には非構造部材の耐震性が確保されているかも確認しましょう。
非常用発電機の設置
大規模な災害が発生すると、広範囲で長期間の停電が発生する可能性が高くなります。現代のビジネスは電力に大きく依存しており、停電は事業活動の全面的な停止を意味します。そこで不可欠となるのが「非常用発電機」です。
非常用発電機は、商用電源が途絶えた際に自動的に起動し、ビルに必要な電力を供給する設備です。この設備の有無とスペックが、停電時の事業継続能力を大きく左右します。チェックすべきポイントは以下の通りです。
- 電力供給の対象範囲: 発電機が供給する電力は、ビルによって異なります。「共用部のみ(エレベーター、廊下の照明、給排水ポンプなど)」を対象とするビルと、「専有部(テナントが使用するオフィス空間)の一部または全部」まで供給するビルがあります。BCPを重視するならば、自社のオフィス内のコンセントに電力が供給されることが望ましいです。特に、サーバーや基幹システムを自社内に設置している場合は、それらを稼働させるための電力が確保できるかが死活問題となります。
- 連続稼働時間: 発電機の稼働時間は、備蓄している燃料の量によって決まります。一般的なビルでは24時間程度の稼働を想定していますが、BCP対応を強化したビルでは48時間や72時間といった長時間の連続稼働が可能な大容量の燃料タンクを備えています。首都直下地震などでは、電力の復旧に3日以上かかるとも言われており、72時間程度の稼働能力は大きな安心材料となります。
- 燃料の補給体制: 72時間を超えるような長期の停電に備え、災害時でも燃料を補給できる体制が整っているかどうかも重要です。ビル管理会社が、燃料供給会社と災害時の優先供給契約を結んでいるかなどを確認しておくと良いでしょう。
非常用発電機は、単に明かりを灯すためだけのものではありません。情報システムを維持し、通信手段を確保し、空調を動かして執務環境を維持するなど、停電下で事業を継続するための生命線です。ビル選定の際には、発電機のスペックを詳細に確認することが極めて重要です。
給排水設備の確保
停電と並んで深刻なのが「断水」です。水道管の破損などにより水の供給が止まると、飲料水の確保はもちろん、トイレの使用や手洗い、清掃、さらには空調システム(冷却水を使用するタイプの場合)の停止など、事業活動と従業員の健康に多大な影響を及ぼします。
オフィスビルの給排水設備に関するBCP対策としては、以下の点が挙げられます。
- 受水槽・高架水槽の確保: 多くのビルでは、水道本管から一度「受水槽」に水を貯め、それをポンプで屋上の「高架水槽」に汲み上げてから各階に給水しています。この受水槽に貯められた水が、断水時の備えとなります。 受水槽の容量が大きいほど、長時間にわたって水の供給を維持できます。また、受水槽やそれを支える架台自体の耐震性も重要です。
- トイレの確保: 断水時に最も問題となるのがトイレです。水が流せなくなると衛生環境が著しく悪化し、感染症の発生源にもなりかねません。対策として、以下のような設備が考えられます。
- 井戸水の活用: 敷地内に井戸を掘り、災害時にはその水をろ過してトイレの洗浄水などに利用するビルもあります。
- 中水(雑用水)利用システム: 雨水や厨房排水などを処理して、トイレの洗浄水として再利用するシステムです。
- 災害用マンホールトイレ: 下水道管に直接接続できる仮設トイレを設置するための設備です。
- 排水機能の維持: たとえ給水が確保できても、停電で排水ポンプが停止すると、地下の汚水槽が満水になり、最終的に排水ができなくなることがあります。排水ポンプが非常用電源に接続されているかを確認することも重要です。
飲料水については、各テナントが備蓄することが基本ですが、トイレ用水のように大量に必要となる水は、ビル全体の設備として確保されていることが望ましいです。清潔なトイレ環境は、従業員の心身の健康を維持し、オフィスに留まって業務を継続するための必須条件と言えるでしょう。
水害・浸水への備え
近年、ゲリラ豪雨や大型台風による都市型水害のリスクが年々高まっています。地震だけでなく、水害・浸水への備えもBCPの重要な柱です。特に、河川の近くや海抜の低い土地に立地するビルでは、対策の有無が事業継続を大きく左右します。
主な水害対策は以下の通りです。
- 重要設備の高層階への設置: ビルの機能を司る電気室、発電機室、サーバー室、通信機械室といった重要設備が、地下や1階ではなく、2階以上の浸水リスクが低いフロアに設置されているかは、極めて重要なチェックポイントです。これらの設備が浸水すると、ビル全体の機能が完全に麻痺してしまい、復旧に長期間を要します。
- 止水板・防水扉の設置: 建物の出入り口や駐車場入口、換気口など、水の侵入口となりうる箇所に止水板や防水扉が設置されているかを確認します。これにより、建物内への浸水を物理的に防ぐことができます。設置されているだけでなく、いざという時に迅速に作動させられるよう、定期的な点検や訓練が行われているかも重要です。
- 排水ポンプの能力: 万が一敷地内や建物内に水が侵入した場合に備え、それを強制的に外部へ排出するための排水ポンプの能力も確認しましょう。また、停電時にも稼働できるよう、非常用電源に接続されていることが必須です。
これらの物理的な対策に加え、自治体が公表している「ハザードマップ」で、ビルの立地がどの程度の浸水深を想定されているエリアなのかを事前に確認しておくことも基本中の基本です。想定される浸水深に対して、ビルの対策が十分であるかを評価することが大切です。
災害用備蓄品の確保
災害発生後、交通機関が麻痺し、多くの従業員が帰宅困難者となる事態が想定されます。また、救助や復旧活動が本格化するまでの間、オフィス内に留まって安全を確保する「籠城」が必要になる場合もあります。このような状況に備え、最低でも3日分、可能であれば1週間分の災害用備蓄品を確保しておくことが強く推奨されます。
備蓄は、ビル管理者が共用部に備える「ビル全体の備蓄」と、各テナント企業が自社の従業員のために専有部に備える「テナントの備蓄」の両輪で考える必要があります。
| 備蓄品カテゴリ | 具体例 | 備考 |
|---|---|---|
| 水・食料 | ・飲料水(1人1日3リットル目安) ・アルファ米、乾パン、缶詰、栄養補助食品など |
・アレルギー対応食も考慮に入れる。 ・調理不要で食べられるものが望ましい。 |
| 衛生用品 | ・簡易トイレ、凝固剤、消臭袋 ・トイレットペーパー、ティッシュペーパー ・手指消毒液、ウェットティッシュ ・歯磨きシート、マスク、生理用品 |
・トイレ問題は特に深刻化しやすいため、十分な量を確保する。 ・感染症対策としても重要。 |
| 救護・安眠用品 | ・救急セット(絆創膏、包帯、消毒薬、常備薬など) ・毛布、アルミ製保温シート ・エアーマット、段ボールベッド |
・体温の維持と休息の確保が体力の消耗を防ぐ。 ・AED(自動体外式除細動器)の設置場所と使い方を確認しておく。 |
| 情報・通信ツール | ・手回し充電式ラジオ ・懐中電灯、ヘッドライト ・予備の乾電池、モバイルバッテリー ・衛星電話 |
・公的な情報や社内連絡を確保するための必須アイテム。 ・スマートフォンの充電切れに備える。 |
| その他 | ・軍手、ヘルメット ・ホイッスル ・ガムテープ、油性ペン、ロープ ・現金(小銭を含む) |
・がれきの撤去や救助活動、伝言などに役立つ。 ・公衆電話や自販機用に小銭も用意する。 |
これらの備蓄品をただ保管するだけでなく、定期的に賞味期限・使用期限をチェックし、入れ替えることが重要です。食料品などについては、古いものから消費し、消費した分を買い足していく「ローリングストック法」を実践することで、無駄なく常に新しい備蓄を維持できます。ビルによっては、こうした備蓄品の管理や入れ替えを代行してくれるサービスを提供している場合もあります。ハード面の設備と合わせて、こうした備蓄体制がどうなっているかを確認することも、ビル選定の重要なポイントです。
オフィスビルのBCP対策|ソフト面の具体例
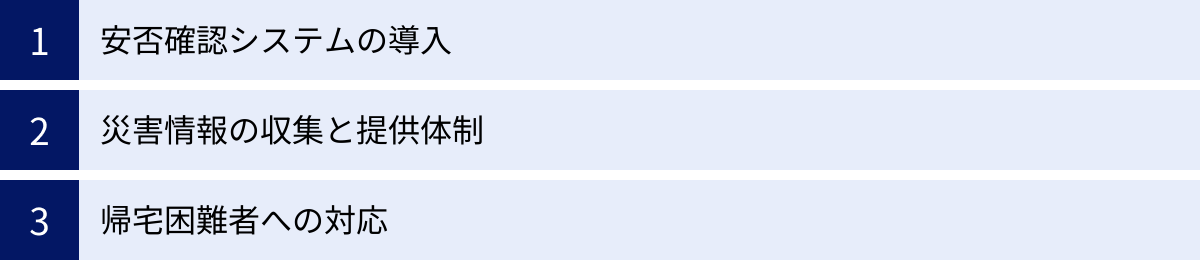
強固な建物や最新の設備といった「ハード面」の対策だけでは、BCPは機能しません。それらをいざという時に最大限に活用し、組織として円滑に行動するための計画や体制、ルールといった「ソフト面」の対策が両輪となって初めて、実効性のあるBCPが実現します。ここでは、オフィスビルにおけるソフト面の具体的な取り組みについて解説します。
安否確認システムの導入
災害発生後のBCP発動における最初の、そして最も重要なアクションが「従業員の安否確認」です。事業を継続・復旧させるためには、どのくらいの人的リソース(従業員)が無事で、稼働可能な状態にあるのかを迅速に把握する必要があります。この初動が遅れると、その後のすべての対応が後手に回ってしまいます。
電話やメールでの連絡は、災害時には通信網の輻輳(ふくそう)により、ほとんど機能しないと考えなければなりません。そこで有効となるのが「安否確認システム」です。
安否確認システムは、災害発生を検知すると、あらかじめ登録された従業員のスマートフォンやPCに、安否状況の報告を求めるメッセージを一斉に自動送信します。従業員は、送られてきたURLにアクセスし、「無事です」「軽傷です」「出社可能です」といった自身の状況を簡単な操作で報告します。管理者は、集まった回答をシステム上でリアルタイムに集計・確認できるため、電話をかけ続けるといった非効率な作業から解放されます。
安否確認システムを導入・運用する上でのポイントは以下の通りです。
- システムの選定:
- 確実な配信: 地震の震度と連動した自動配信機能や、複数の連絡手段(アプリのプッシュ通知、メール、SMSなど)に対応しているか。
- 簡単な操作性: 従業員が迷わず直感的に回答できるシンプルなインターフェースか。管理者側の集計画面は見やすいか。
- 付加機能: 本人の安否だけでなく、家族の安否も報告できる機能や、自由記述が可能な掲示板機能、備蓄品の在庫確認や出社要否を問うアンケート機能など、自社の運用に合った機能があるか。
- 多言語対応: 外国籍の従業員がいる場合は、多言語に対応しているかも重要な選定基準です。
- 導入後の運用:
- 個人情報登録の徹底: 全従業員にシステムへ連絡先を登録してもらう必要があります。BCPの重要性を丁寧に説明し、登録を徹底させることが不可欠です。
- 定期的な訓練の実施: システムを導入しただけで満足してはいけません。「防災の日」などを利用して、年に1〜2回は全社的な安否確認訓練を実施しましょう。訓練を通じて、従業員は操作に慣れ、管理者は回答率が低い従業員へのフォローや、運用上の課題を洗い出すことができます。
- 安否確認後の行動計画: 安否確認は、情報を集めるだけで終わりではありません。「安否が確認され、出社可能と回答した従業員のうち、誰が、いつ、どこに出社するのか」、あるいは「在宅勤務に切り替えるのか」といった、次のアクションを指示するためのルールをあらかじめ定めておく必要があります。この指示伝達も、安否確認システムの掲示板機能などを活用して行うことができます。
安否確認は、従業員の安全を確保するという最重要課題を達成するための第一歩であると同時に、事業復旧に必要な人的資源を把握し、BCPを次のフェーズに進めるための羅針盤となる、極めて重要なソフト面の対策です。
災害情報の収集と提供体制
災害時には、デマや不確かな情報が錯綜し、人々の不安を煽り、誤った判断や行動を誘発することがあります。パニックを抑え、従業員が安全かつ的確に行動するためには、「正確な情報を、迅速に収集し、分かりやすく提供する」体制を構築しておくことが不可欠です。
情報収集と提供の体制を構築する上でのポイントは以下の通りです。
- 信頼できる情報源の確保:
- 公的機関: 気象庁、国土地交通省、内閣府、地方自治体などのウェブサイトや公式SNSアカウントは、最も信頼性の高い情報源です。
- 報道機関: テレビ、ラジオ、新聞社のウェブサイトなども重要な情報源となります。特にラジオは停電時にも情報収集できる貴重なメディアです。
- 交通機関: JRや私鉄、バス会社などの運行情報サイトは、従業員の出社・帰宅判断に不可欠です。
- 災害情報サービス: 近年では、SNSの投稿などをAIで解析し、事件・事故・災害の情報をリアルタイムで配信する法人向けのサービスも登場しています。こうしたサービスを活用することで、より早く、ピンポイントな情報を得ることが可能になります。
- 情報集約と判断の体制:
- 収集した多岐にわたる情報を、誰が(例:本社対策本部)、どのように集約し、その情報に基づいてどのような判断を下すのか(例:出社禁止、在宅勤務への切り替え、ビルの閉鎖など)、役割分担と意思決定のプロセスを明確に定めておく必要があります。
- この体制は、役職者が被災して不在の場合も想定し、代理権限者やバックアップ体制も決めておくことが重要です。
- 従業員への情報提供手段:
- ビル管理会社との連携: 多くのBCP対応ビルでは、災害時にビル管理会社が館内放送や共用部のデジタルサイネージ、一斉メールなどで、ビルの被災状況、インフラ(電気・水道・ガス)の状態、周辺地域の情報などを提供してくれます。ビル側からどのような情報が、どのタイミングで提供されるのかを事前に確認し、自社の情報伝達計画に組み込んでおきましょう。
- 自社の伝達チャネル: 前述の安否確認システムの掲示板機能や、ビジネスチャットツール、社内SNS、緊急連絡網などを活用し、会社の公式方針や具体的な指示を全従業員に伝達します。複数の伝達手段を確保しておくことで、一つの手段が機能しない場合のリスクを分散できます。
正確な情報は、従業員の命を守り、事業復旧を正しい方向に導くための「光」です。平時から情報収集・提供の体制を整え、訓練を重ねておくことが、混乱を乗り越えるための鍵となります。
帰宅困難者への対応
首都直下地震などの大規模災害が発生した場合、鉄道などの公共交通機関は一斉に運行を停止することが予想されます。その結果、特に都心部のオフィスでは、多くの従業員が自宅に帰れなくなる「帰宅困難者」となる事態が想定されます。東京都の条例では、事業者に対して、従業員を施設内に待機させるなどの「むやみに移動を開始しない」ことを徹底させる努力義務を課しています。これは、大勢の人が一斉に徒歩で帰宅を始めると、救急・消防活動の妨げになったり、群集雪崩などの二次災害を引き起こしたりするリスクがあるためです。
この原則に基づき、企業は従業員を安全に社内に留まらせるための「帰宅困難者対応計画」を策定しておく必要があります。
- 一時滞在施設の設営計画:
- 災害発生後、従業員が安全に待機できるスペースをあらかじめ決めておきます。オフィスの会議室やリフレッシュスペースなどを「一時滞在施設」として指定し、何人程度を収容できるかを把握しておきます。
- そのスペースを設営するための手順(机や椅子をどう配置するか、情報提供用のモニターをどこに置くかなど)も計画しておくと、スムーズな対応が可能です。
- 備蓄品の提供:
- ハード面の対策で述べた備蓄品(水、食料、毛布、簡易トイレなど)を、待機している従業員に公平に配布するためのルールや担当者を決めておきます。誰が、どこで、何を配布するのかを明確にしておくことが混乱を防ぎます。
- 情報提供と精神的ケア:
- 待機している従業員の不安を和らげるため、ラジオやテレビ、インターネットなどを通じて、交通機関の復旧見込みや、地域の被害状況、公的な避難所の情報などを継続的に提供します。
- 管理職や対策本部のメンバーが定期的に巡回し、声をかけるなど、精神的なケアにも配慮することが重要です。
- 帰宅支援:
- 交通機関が一部復旧したり、安全が確認されたりした後には、従業員の安全な帰宅を支援します。
- 時差退社の指示: 混乱を避けるため、方面別や部署別に時間をずらして帰宅させる計画を立てます。
- 安全な帰宅ルートの情報提供: 自治体が設定する「災害時帰宅支援ステーション(コンビニやガソリンスタンドなどで、水道やトイレ、情報提供の支援を受けられる場所)」を経由する安全なルートマップなどを用意しておくと有効です。
- 来訪者への対応:
- 自社の従業員だけでなく、災害発生時に社内にいた来訪者(顧客や取引先など)への対応も忘れてはなりません。可能な範囲で、一時的な待機場所や情報、備蓄品を提供できるよう、あらかじめ方針を決めておくことが企業の社会的責任として求められます。
帰宅困難者への対応は、従業員の安全を守ることはもちろん、社会全体の混乱を抑制するという大きな目的も持っています。自社の都合だけでなく、社会の一員としての責任を果たすという視点で、実効性のある計画を策定・周知しておくことが重要です。
BCP対策に強いオフィスビルを選ぶ4つのチェックポイント
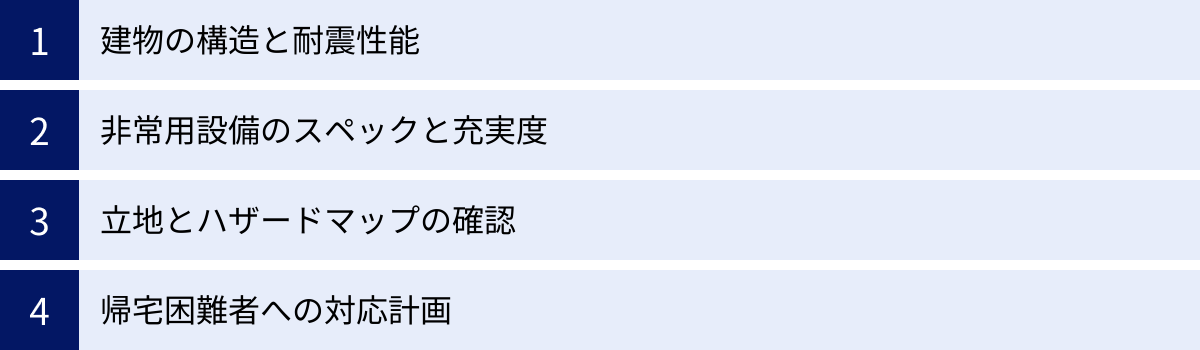
これからオフィスの移転や新設を検討している企業にとって、ビルのBCP性能は、賃料や立地、デザインと並ぶ、あるいはそれ以上に重要な選定基準となります。ここでは、BCP対策に強いオフィスビルを見極めるための4つの具体的なチェックポイントを解説します。
① 建物の構造と耐震性能
まず確認すべきは、従業員の生命と企業の資産を物理的に守る、建物の基本的な安全性です。
- 耐震・制震・免震の構造: 前述の通り、3つの構造にはそれぞれ特徴があります。自社の事業特性(精密機器の有無、データセンターの設置など)や予算に合わせて、最適な構造のビルを選定しましょう。 特に事業継続性を最優先するならば、揺れ自体を大幅に低減できる免震構造が最も望ましい選択肢となります。
- 新耐震基準への適合: 1981年6月1日以降に建築確認を受けた「新耐震基準」の建物であることは最低条件です。可能であれば、2000年に改正された、より厳しい基準(地盤調査の義務化など)を満たしているかどうかも確認しましょう。
- 耐震診断と補強の履歴: 新耐震基準を満たしているビルでも、より詳細な「耐震診断」を実施している場合があります。その診断結果(Is値など、耐震性能を示す指標)を開示してもらい、安全性を客観的に評価しましょう。旧耐- 震基準のビルであっても、適切な耐震補強工事が実施されていれば、新耐震基準と同等以上の性能を持つ場合もあります。工事の履歴や内容を確認することが重要です。
- 非構造部材の耐震対策: 天井材が地震で落下しないような工法(特定天井など)が採用されているか、間仕切り壁や窓ガラスに飛散防止対策が施されているか、大型の照明器具がしっかりと固定されているかなど、構造体以外の部分の安全性も内覧時に必ずチェックしましょう。これらの対策は、直接的な人的被害を防ぐ上で非常に重要です。
- 定期的なメンテナンス状況: 建物の性能は、経年劣化によって低下します。ビル管理会社が、定期的な建物診断やメンテナンスを計画的に実施しているかどうかも、長期的な安全性を担保する上で大切なポイントです。
② 非常用設備のスペックと充実度
災害によるライフラインの寸断にどれだけ耐えられるかは、非常用設備の性能にかかっています。カタログスペックだけでなく、実際の運用まで踏み込んで確認しましょう。
- 非常用発電機:
- 連続稼働時間: 「72時間以上」を一つの目安としましょう。
- 給電範囲: 共用部だけでなく、自社が利用する専有部内のコンセントに電力が供給されるかは必ず確認が必要です。「BCP用コンセント」として、どのくらいの容量(アンペア)まで利用できるのかを具体的にヒアリングしましょう。
- 燃料備蓄と補給体制: 燃料タンクの容量と、災害時の燃料補給契約の有無を確認します。
- 給排水設備:
- 受水槽の容量: ビルの収容人数に対して十分な容量があるか。断水後、何日間程度トイレや手洗いが使用可能かの目安を確認します。
- トイレの代替手段: 井戸水や中水の利用システム、マンホールトイレなどの特別な設備があるかは、大きな付加価値となります。これらの設備がない場合は、自社で十分な量の簡易トイレを備蓄する必要があります。
- 排水ポンプの電源: 排水ポンプが非常用電源に接続されているか。地下階があるビルでは特に重要なチェック項目です。
- 空調設備:
- 非常用電源で空調(特に冷房)が稼働するかを確認します。特に、サーバー室など熱を発する機器を多く設置する区画では、空調の停止がシステムダウンに直結するため、必須の確認項目です。
- 通信設備:
- 複数キャリアの引き込み: 特定の通信キャリアの基地局が被災した場合に備え、複数の通信事業者の回線がビルに引き込まれているか(マルチキャリア対応)を確認します。
- バックアップ回線: ビルとして衛星電話や専用線などのバックアップ回線を用意している場合もあります。
- エレベーター:
- 地震発生時に最寄り階に自動停止し、ドアが開く「地震時管制運転装置」が設置されていることは基本です。さらに、停電時にもバッテリーで最寄り階まで移動できる「停電時自動着床装置」があると、閉じ込めリスクを低減できます。
③ 立地とハザードマップの確認
どんなに強固なビルでも、立地している土地そのものに高いリスクがあっては意味がありません。客観的なデータに基づいて、立地の安全性を評価しましょう。
- 各種ハザードマップの確認:
- 入居を検討している地域の自治体が公表している「洪水ハザードマップ」「地震ハザードマップ(揺れやすさマップ、液状化マップなど)」「津波・高潮ハザードマップ」「土砂災害ハザードマップ」などを必ず確認します。
- ビルの所在地が、浸水想定区域や液状化の可能性が高いエリアに含まれていないか、含まれている場合は、それに対する十分な対策(建物の嵩上げ、地盤改良など)が講じられているかを確認します。
- 交通アクセス:
- 複数の鉄道路線・駅が利用できる立地は、災害時に一つの路線が不通になっても、別のルートで通勤できる可能性が高く、事業復旧の観点から有利です。
- 主要な幹線道路へのアクセスが良いかも、緊急車両の通行や物資輸送のしやすさに関わってきます。
- 周辺地域の安全性:
- 木造住宅が密集している地域に隣接している場合、地震火災の際の「延焼リスク」が高まります。
- 周辺に危険物施設(ガソリンスタンド、化学工場など)がないかも確認しておきましょう。
- 避難場所との位置関係:
- 万が一ビルからの退去が必要になった場合に備え、指定されている「広域避難場所」や「一時(いっとき)集合場所」がどこにあり、ビルから安全に到達できるルートが確保されているかを確認しておきます。
これらの情報は、不動産仲介会社からの情報だけでなく、必ず自社の担当者が自治体のウェブサイトなどで一次情報を確認することが重要です。
④ 帰宅困難者への対応計画
従業員を災害時に「むやみに移動させない」原則を守るためには、ビル全体としての受け入れ体制が不可欠です。テナント任せにせず、ビル管理会社が主体的に関わっているかを見極めましょう。
- ビル全体のBCP:
- ビル管理会社が、ビル全体としてのBCP(または災害対策マニュアル)を策定し、テナントに開示しているかを確認します。その内容が具体的で、実効性のあるものかを見極めます。
- 共用部での備蓄:
- ビルとして、帰宅困難者向けの備蓄品(水、食料、毛布、簡易トイレなど)を共用部に用意しているか、その内容と量(収容想定人数に対して十分か)を確認します。
- 一時滞在スペースの指定:
- 災害時に帰宅困難者のための一時滞在スペースとして開放される場所(エントランスホール、共用会議室など)が明確に指定されているか、またその収容可能人数を確認します。
- 情報提供体制:
- 災害時にビル管理会社からテナントに対して、どのような情報(ビルの被害状況、ライフラインの復旧見込みなど)が、どのような手段(館内放送、掲示板、メールなど)で提供されるのか、その体制が明確になっているかを確認します。
- テナントとの連携:
- ビル管理会社とテナント各社が参加する、定期的な防災訓練や連絡協議会が実施されているかは、連携体制の成熟度を測る良い指標となります。災害はビル全体で乗り越えるものであるという共通認識が醸成されているビルは、信頼性が高いと言えるでしょう。
これらの4つのポイントを、チェックリストとして活用し、複数の候補ビルを比較検討することで、自社の事業と従業員を守るにふさわしい、最適なオフィスビルを選び出すことが可能になります。
オフィスビルのBCP対策を強化するツール・サービス3選
自社でBCPのすべてをゼロから構築・運用するのは、多大な労力と専門知識を要します。幸いなことに、現代ではBCP対策の各フェーズを効率化し、強化するための様々なツールやサービスが存在します。ここでは、特にオフィスビルのBCPにおいて有効な3つの代表的なサービスを紹介します。
※以下に記載するサービス内容や機能は、各社の公式サイトの情報に基づいています。(2024年5月時点)
① 安否確認システム:安否確認サービス2(トヨクモ株式会社)
災害発生時の初動対応の要である従業員の安否確認を、迅速かつ確実に行うためのクラウドサービスです。
主な特徴と機能:
- 自動配信機能: 気象庁が発表する震度情報と連動し、設定した震度以上の地震が発生した場合に、対象地域の従業員へ安否確認メッセージを自動で一斉配信します。これにより、担当者が手動で操作する必要がなく、夜間や休日でも確実な初動が可能です。
- 多彩な通知手段: スマートフォンアプリへのプッシュ通知、メール、SMS(ショートメッセージサービス)など、複数の手段で通知を送ることができます。どれか一つの通信網が機能しなくても、別の手段で従業員にリーチできる可能性が高まります。
- 直感的な操作と自動集計: 従業員は受け取ったメッセージから簡単に自身の状況(「無事です」「軽傷です」など)を報告できます。報告されたデータはリアルタイムで自動集計され、管理者はPCやスマホの管理画面から、部署別・状況別などで被害状況を即座に把握できます。
- 家族の安否確認・掲示板機能: 従業員本人のみならず、事前に登録した家族の安否を報告・確認できる機能や、従業員同士で情報交換ができる掲示板機能も備わっています。これにより、従業員の不安を軽減し、コミュニケーションを促進します。
- kintone連携: サイボウズ社の業務改善プラットフォーム「kintone」との連携に強みがあり、安否確認の結果をkintone上の顧客情報や案件情報と突き合わせるなど、より高度なデータ活用も可能です。
(参照:トヨクモ株式会社 公式サイト)
BCPにおける活用ポイント:
このサービスを導入することで、BCPの最重要課題である「人的リソースの把握」を劇的に効率化できます。手作業での電話連絡などにかけていた時間を、対策本部の設置や事業復旧の具体的な指示といった、より重要な業務に充てられるようになります。「誰が、どこで、どのような状況か」を迅速に可視化することは、その後の全てのBCP活動の起点となります。導入と合わせて定期的な訓練を実施することで、災害対応能力を飛躍的に高めることができます。
② 災害情報サービス:FASTALERT(株式会社JX通信社)
SNSをはじめとする膨大な情報の中から、AIを活用して災害・事故・事件などのリスク情報をリアルタイムで検知・配信する法人向けの情報サービスです。
主な特徴と機能:
- 圧倒的な速報性: 一般的な報道機関よりも早く、SNSへの投稿などから事件・事故の発生を検知し、ユーザーに通知します。火災やインフラ障害、交通情報などをいち早く把握することで、対応の先手を打つことができます。
- 情報の正確性と網羅性: 収集した情報をAIと人の目で分析し、情報の信頼性を高めた上で配信します。デマや誤情報に惑わされるリスクを低減できます。対応するリスク情報の種類も、自然災害だけでなく、火災、事件・事故、交通障害、ライフライン情報など多岐にわたります。
- ピンポイントな情報収集: 自社のオフィスや工場、店舗、サプライヤーの所在地などを登録しておくことで、その地点周辺で発生したリスク情報だけをプッシュ通知で受け取ることができます。膨大な情報の中から、自社に関連する重要な情報だけを効率的に収集できます。
(参照:株式会社JX通信社 公式サイト)
BCPにおける活用ポイント:
FASTALERTは、BCPにおける「情報収集・提供体制」を強力にバックアップします。災害発生時に「自社の拠点の周辺で何が起きているのか」「サプライチェーンに影響はないか」「従業員の通勤経路は安全か」といった状況を、どこよりも早く正確に把握するのに役立ちます。これにより、対策本部は客観的な情報に基づいて、より的確な意思決定を下すことが可能になります。例えば、オフィスの最寄り駅で火災が発生したという情報をいち早く察知し、従業員に在宅勤務を指示するといった、プロアクティブな危機管理が実現します。
③ 備蓄品管理サービス:あんしんストック(プラス株式会社)
BCP対策に不可欠な災害用備蓄品の選定から購入、在庫管理、賞味期限管理、補充までをワンストップで代行してくれるサービスです。
主な特徴と機能:
- コンサルティングと選定: 企業の従業員数やオフィスの状況に合わせて、どのような備蓄品が、どのくらい必要かを専門家が提案してくれます。何から揃えれば良いか分からないという企業の悩みを解決します。
- 一元管理システム: 納品された備蓄品はWeb上の管理システムに登録され、何を、どこに、いくつ保管しているかを簡単に可視化できます。複数拠点がある場合でも、全社の備蓄状況を一元的に把握できます。
- 期限管理と自動通知: 備蓄品の賞味期限や使用期限が近づくと、システムから自動でアラートメールが届きます。これにより、「いざ使おうとしたら期限が切れていた」という事態を防ぎます。
- 入れ替え・補充の代行: 期限が近づいた備蓄品の回収と、新しい備蓄品の納品を代行してくれます。担当者が入れ替え作業に手間をかける必要がなく、ローリングストックを効率的に実践できます。
(参照:プラス株式会社ジョインテックスカンパニー 公式サイト)
BCPにおける活用ポイント:
備蓄品の管理は、日常業務の中では後回しにされがちな「重要だが緊急ではない」業務の典型例です。結果として、担当者任せになり、異動や退職によって管理が形骸化してしまうケースが少なくありません。「あんしんストック」のようなサービスを利用することで、備蓄品管理を属人化から解放し、組織として継続的かつ確実に実行できる仕組みを構築できます。これにより、総務部門などの担当者は管理業務の負担から解放され、より戦略的なBCPの企画・立案に注力できるようになります。確実な備蓄は、帰宅困難者対応や籠城シナリオの実現性を担保する上で、不可欠な基盤です。
これらのツールやサービスは、それぞれがBCPの特定の側面を強化するものですが、組み合わせて活用することで、より強固で実効性の高いBCP体制を構築することが可能になります。
まとめ
本記事では、オフィスビルにおけるBCP対策の重要性から、その根幹をなす考え方、そしてハード面・ソフト面における具体的な取り組みまでを、幅広く解説してきました。
改めて強調したいのは、現代のビジネス環境において、BCPはもはや「任意」の取り組みではなく、企業の存続と持続的成長を左右する「必須」の経営課題であるという点です。予期せぬ災害や危機は、いつ、どこで発生するか分かりません。その時に、事業と従業員を守り、社会的な責任を果たせるかどうかは、平時からの備えにかかっています。
オフィスビルのBCP対策を成功させる鍵は、「ハード(物理的な設備)」と「ソフト(運用計画・体制)」の両輪をバランス良く回していくことにあります。免震構造や72時間稼働の非常用電源といった強固なハードウェアも、それを使いこなすための安否確認体制や情報伝達ルールといったソフトウェアがなければ宝の持ち腐れです。逆に、どんなに優れた計画も、それを支える物理的な基盤が脆弱では絵に描いた餅となってしまいます。
これからオフィス移転を計画している企業は、本記事で紹介した「BCP対策に強いオフィスビルを選ぶ4つのチェックポイント」を参考に、賃料や立地といった従来の基準に加えて、「事業継続性」という新たなものさしで物件を評価することをおすすめします。
また、すでにオフィスを構えている企業も、決して手遅れではありません。建物の構造を変えることは難しくても、安否確認システムや備蓄品管理サービスといったツールを活用したり、帰宅困難者対応計画を見直したりするなど、ソフト面を中心に強化できることは数多くあります。
最後に、最も重要なことをお伝えします。それは、BCPは一度策定して終わりではない、ということです。事業内容の変化、技術の進歩、そして新たなリスクの出現に合わせて、計画は常にアップデートされなければなりません。そして、その計画が本当に機能するかどうかを確かめる唯一の方法は、定期的な教育と訓練を繰り返すことです。訓練を通じて課題を発見し、計画を改善していく地道なサイクルこそが、生きたBCPを育み、企業の真のレジリエンス(強靭性)を構築するのです。
この記事が、皆様の企業が不確実性の高い時代を乗り越え、力強く成長を続けていくための一助となれば幸いです。